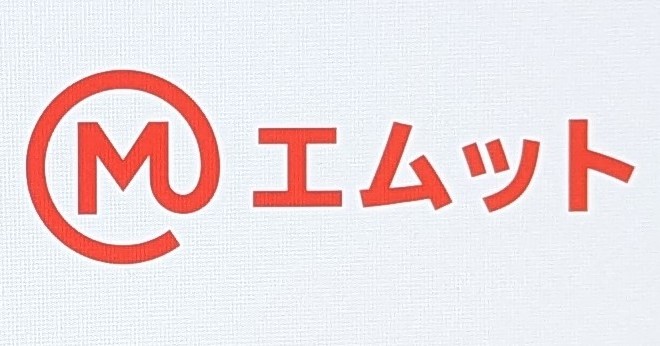それでもタイを離さない!日系自動車メーカーが選ぶ、強靭なサプライチェーン戦略とは?

2011年の大規模洪水、世界的な金融危機、そして通貨暴落… 幾多の困難が待ち受けるタイ。しかし、多くの日系企業、特に自動車メーカーにとって、タイは依然として重要な生産拠点であり、その地位を譲りません。本記事では、なぜ日系企業がタイを離れず、むしろその重要性を増しているのか、その背景にある強靭なサプライチェーン戦略に迫ります。
2011年、タイを襲った大洪水と日系企業の決断
2011年11月、タイは記録的な大洪水を経験しました。多くの工場が浸水し、生産活動は完全に停止。周辺国での代替生産を検討する企業も少なくありませんでしたが、日系自動車メーカーは異例の決断をしました。それは、操業停止中においても従業員の雇用を確保し、早期の操業再開を目指すというものでした。
この決断は、単なる人道的配慮だけではありません。タイは、日系自動車メーカーにとって、東南アジアにおける重要な生産ハブとしての役割を担っており、そのサプライチェーンにおける戦略的な位置づけは揺るぎないものでした。代替生産拠点を新たに構築するよりも、既存の拠点を維持・強化する方が、長期的な視点で見ればコスト効率が良いと判断されたのです。
日系企業がタイを離さない理由:サプライチェーンの強靭性
日系企業がタイを離さない理由は、単に過去の経験だけではありません。タイは、以下の点で、日系企業のサプライチェーンにとって魅力的な選択肢であり続けています。
- 地理的優位性: 東南アジア諸国へのアクセスが容易であり、輸出拠点として最適
- 熟練した労働力: 自動車産業における豊富な経験と高い技術力を持つ労働力
- 政府の支援: 自動車産業に対する積極的な投資と優遇政策
- インフラ整備: 港湾、道路、鉄道などのインフラが整備されており、物流コストを抑えられる
- 経済成長の安定性: 比較的安定した経済成長を維持しており、長期的な投資に適している
強靭なサプライチェーン戦略:リスク分散と地域密着
日系企業は、タイにおけるサプライチェーンのリスクを認識しており、様々な対策を講じています。その一つが、リスク分散です。複数の工場を異なる地域に配置し、自然災害や政治的なリスクの影響を最小限に抑える戦略です。また、地域密着型のサプライヤーとの連携を強化し、地元の雇用を創出することで、地域社会との良好な関係を築いています。
今後の展望:デジタル化とサステナビリティ
今後のタイにおけるサプライチェーンは、デジタル化とサステナビリティが重要なキーワードとなるでしょう。IoTやAIを活用した生産効率の向上、サプライチェーン全体の可視化、そして環境負荷の低減など、よりスマートで持続可能なサプライチェーンの構築が求められています。
日系企業は、これらの課題に積極的に取り組み、タイにおけるサプライチェーンの競争力をさらに高めていくことが期待されます。